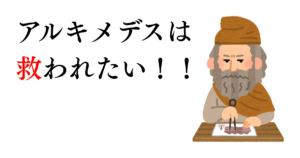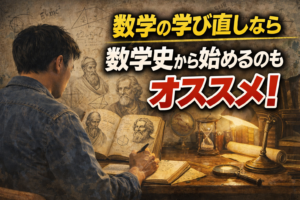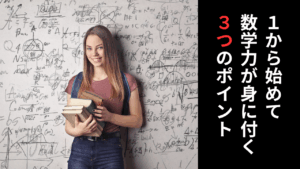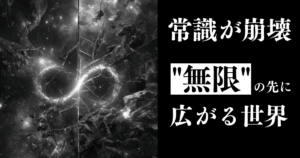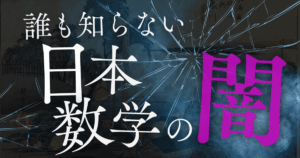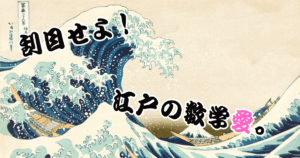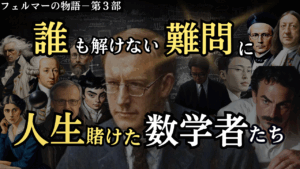微分積分
それは、現代社会のあらゆる場面で使われている科学の根幹といえます。
物体の動きの予測、薬の副作用の解析、天気予報、金融モデル、さらには画像や音声の処理まで。
現代テクノロジーのほとんどを微分積分が支えているのです。
そんな「世界を動かす理論」は、17世紀に、物理学者ニュートンと哲学者ライプニッツが生み出したというのは、驚くべき事実です。
ニュートンが物理学から導いたのに対し、ライプニッツは哲学からたどり着いたのですが。
ライプニッツは、どうしてそんなことが可能だったのでしょうか。
今回は哲学から見た微分積分を解説していきます。
ライプニッツの生涯と業績をザックリ解説
ライプニッツの生涯と業績をザックリ解説します。

ライプニッツ(1646–1716)は、数学者であり、哲学者であり、論理学者でもありました。
幼少期からラテン語の書物を読みこなすほどの天才で、大学では哲学・数学・法学を学び、博士号を取得。
若くして政治や外交の世界に進出し、マインツ大司教に仕えるほどのエリートでした。
しかし1673年、庇護者を失い失職。
これがきっかけで彼を本格的に数学の研究を始める。
パリでホイヘンスら一流科学者とともに切磋琢磨し、独自の数学的才能を開花させた彼は、1675年――ついに微分積分法を発見したのでした。
その後「ニュートンとの発明者論争」が勃発。
「誰が先に思いついたのか」をめぐって、ヨーロッパ中を巻き込む騒動となりましたが、最終的に世界に広まったのは、ライプニッツが考案した「dx」「∫」という記号法。
私たちが今日も使っている「ライプニッツ式」こそ、彼の知の結晶なのです。
彼は他にも、普遍記号学や二進法などの論理も発明しているのです。
晩年のライプニッツは再び哲学に戻り、『モナドロジー』を執筆。
すべての存在を「モナド(単純実体)」として捉える世界観を構築し、1716年にその生涯を閉じました。
そもそも微分積分とは?
微分積分とは、「変化を捉えるための理論」です。
微分積分は、微分学と積分学と別々の学問をまとめた表現ですが、微分とは、「細かく分ける」、積分とは「結合する」となります。
微分:変化の瞬間をとらえる
積分:変化を積み重ねて全体をとらえる
これらは物体の動きをより精密に捉える際にとても有効なのです。
微分とは
例えば、車のスピードを考えてみましょう。
ある車が走っているとき、
1時間後には100km走っていた
2時間後には200km走っていた
このとき、「速さ」はどうなっているでしょうか?
距離の変化を時間で割ると、1時間あたり100km。
これが平均の速さです。
でも現実には、坂道を登ったり信号で止まったりします。
「今この瞬間の速さ(瞬間の変化)」を知りたいとき――
その“瞬間”の変化を求めるのが、微分です。
つまり微分とは、「変化の割合」=「傾き」を求めること。
グラフでいえば、曲線のその点での接線の傾きを求める操作です。
積分とは
だからこそ、微分積分は「現代の科学と言語の共通基盤」ともいえるのです。
今度は逆に考えます。
もし「速さ」がわかっているとき、
どれだけの距離を進んだかを知りたい場合はどうするでしょうか?
たとえば時速が少しずつ変わっているとき、
速さの値を時間ごとに少しずつ足していくことで、全体の距離が出せます。
この「足していく」操作が、積分です。
つまり積分とは、
「変化を積み重ねて、全体を求めること」。
グラフでいえば、曲線とx軸の間の面積を求めることにあたります。
まとめ
ということで、今回はライプニッツの生涯と実績、そして微分積分について解説しました。
次回の記事では、「哲学的視点から、どのように微分積分を発明したのか?」について考察していきます。