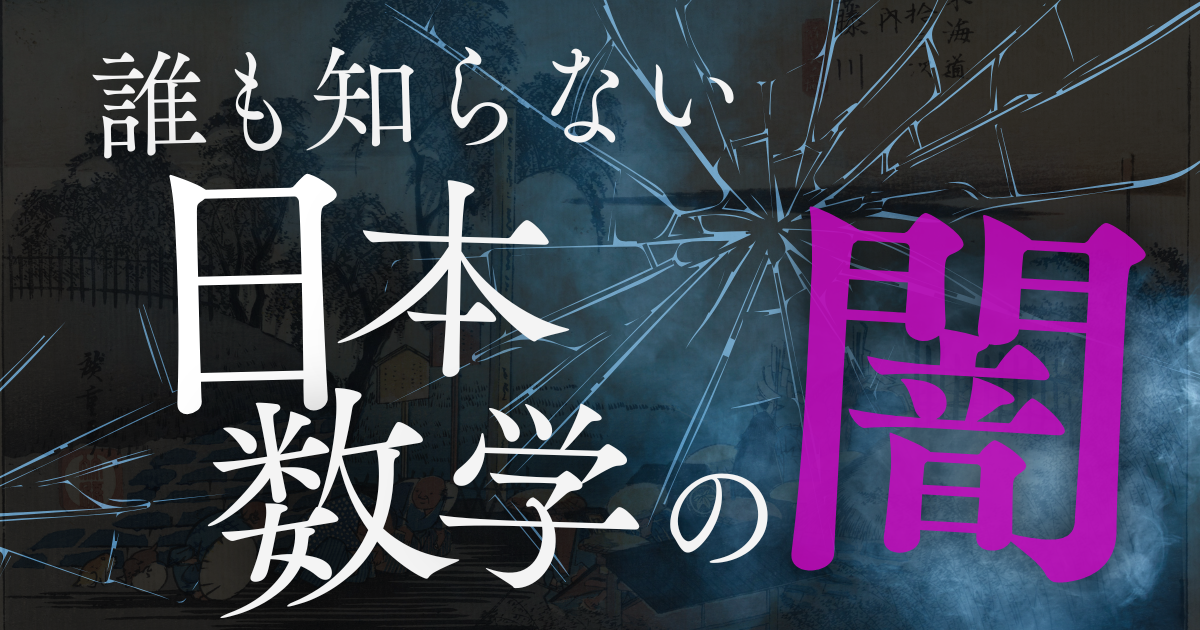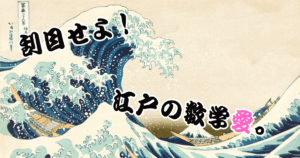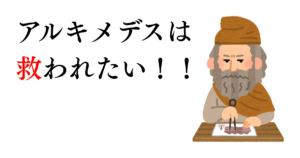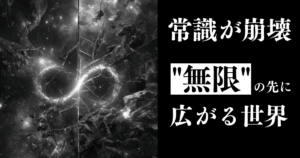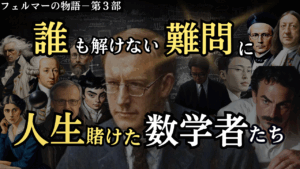どうも丸田です。
以前書いた記事では、江戸時代に花開いた数学文化「和算」の凄さや魅力をご紹介しました。
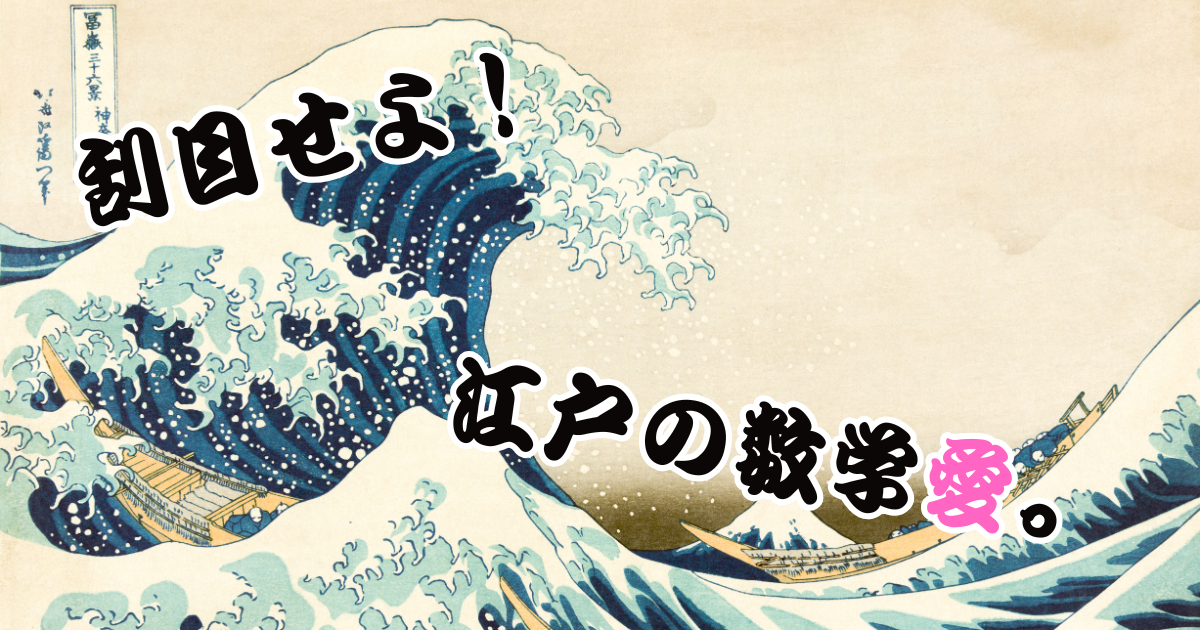
江戸時代の数学は西洋よりも優れていた、という話は実は結構有名だったりします。
しかし、それとは対照的に、実はあまり知られていない江戸時代の数学文化の闇も存在しています。
もちろん、江戸の数学文化はとても素晴らしいものです。
しかし光が強くなれば影も濃くなるように、その良き文化の裏返しこそが、和算消滅の原因ともなり得るのではないかと思うのです。
今回は、和算の栄光の影に隠れた、閉鎖性・非実用性・階級的な偏見など、江戸数学の持つ負の側面に迫ります。
和算って何の役に立つの?和算家と一般人との乖離
江戸時代、全国的にブームとなった和算。
しかし、細かくみていくと、和算家が求めた数学と町人が求めた数学には大きな乖離がありました。
和算家が求めた数学とは、ハイレベルな理論を求めていました。
例えば、高次の方程式の解法や、解微分積分に近いアイデア、また精密な円周率、円の面積や多角形の内角を求め続けていたのです。
時には、誰も解けないような難問を出題し合ったりもしていたのです。
一方、町人が必要としていたのは、実社会を支える道具としての数学でした。
商売の計算、年貢の割り出し、両替のレートなど、日々の暮らしの中で求められたのは、すぐに使える現実的な知識だったのです。
このように、そもそも和算と一言で言っても、実は町人と和算家が求めているものには、大きな方向性の違いがあったのですね。
町人の計算において、最も重宝したのが「そろばん」です。
一方で、和算家はそのような道具を用いずとも、答えが導き出せるような理論の開発に勤しんでいたそうです。
ここからもう目指すものが違っている感じがありますね…苦笑
これは考察にすぎませんが、もしかしたら町人からすれば「和算って何の役に立つの?」と思っていたし、和算家からすれば「町人の数学は邪道だ」と嫌う人もいたのかもしれません。
誰の役に立つわけでもない難問を追い求める和算家と、現実の数字に向き合う町人たち。
同じ「数学」でありながら、その目的も価値観もまったく異なる世界がそこには広がっていたのですね〜。

ちなみに、和算に夢中になりすぎるがあまり、自分の仕事に手がつかなくなったり、事業を潰してしまう人もいたそうです。
もちろん一見役立ちそうになり理論が、後にすごい科学技術を支えるようになる、ということもあります。
例えば、素数が暗号理論に活用されたり、接線を引くという謎に思えるアイデアが、現代の科学を構成する微分積分学に活用されていたり、そんな事例も和多く存在するわけですからね。
なので、江戸の雰囲気が一概にダメとは言えないんじゃね?と思うかもしれません。
が!しかし。
江戸の数学には、「オイオイマジかよ〜」という、もう一つの側面がありました。
超秘密主義の和算
実は和算の世界には、それはもう強い強い秘密主義が存在していました。
江戸時代の日本には、各地に和算塾が開かれていましたが、そこへ入門するには、契約書を書かされたそうです。
それも「学んだことを口外しない」という内容を。



紀元前のギリシャで数学者であり宗教家でもあったピタゴラスと同じやり口です。
そう!江戸の数学は、それぞれ流派があり、それらの流派は他者と共有してはいけないのですね。
しかも、「たとえ親兄弟であっても他言無用」という徹底ぶり。
そのため、和算は学問的な自由の発展よりも、流派内の序列や免許制度を守ることが優先されており、いわばとても閉鎖的な状況だったのです。
町人は日々の役立つ数学さえわかれば良いのです。
だからこそ、最先端の理論を知ることが難しい状況でもあり、ますます町民が和算家の研究への興味を失います。
その結果、和算は一般の実生活からますます乖離し、庶民の手の届かない暗黒世界へと進んで行ったのです。



これでは、高度な和算を日常に応用させようというモチベーションも生まれづらいですよね。
とまぁ、こんな感じで和算という、世界的にも凄い!とされる日本数学ですが、闇の一面も見れたのではないでしょうか?笑
しかし、実はまだここでは終わりません笑
数学を嫌った武士たち
当時は、武士たちは数学を毛嫌いしており、数学は「下っ端役人が行う卑しい学問」と見なされていたのです。
そのため、学ぶこと自体が恥とされていました。
なぜかというと、「武士は清貧であるべき」という価値観があったからです。
数字の計算は、主に商人が売上や銭勘定のために使うものであり、「金銭に細かい=卑しい」という感覚がありました。
そのため、計算を学ぶという行為そのものが、商人の真似事のように思われ、武士にとっては名誉を傷つける行為とされていたのですね。
とは言え、武士の中にも、実は数学が好きな人も一定数いました。
そのような武士は、夜中にこっそり書物を開き、人目を避けながら勉強していたと言われています。
「数学を学んでいることが知られれば、友人から絶交されかねない」──そんな空気すらあったのです。
ちなみに、「学問のすすめ」で知られる福沢諭吉も、幼少の頃に父親から「数学などは身分の低い者がやることだ」と言われ、学習を禁じられた経験があったとされています。
このように、当時の武士の価値観が、数学の社会的地位を押し下げていたという側面があります。
このように、町人と和算家、そして武士。
彼らが各々数学に対してバラバラな価値観を持っていたのです。
しかし、やがて幕末に差しかかり、西洋から軍事や科学の技術が流入しはじめると、否応なしに高度な数学の知識が求められるようになります。
しかしそのとき、国内に「数学を学んできた人材」が決定的に不足していたのです。
これが和算消滅の布石になったと考えられるのです。
黒船来航!和算の終焉
1853年、ペリー率いる黒船の来航は、日本の数学界にも衝撃を与えました。
一気に日本に国防意識が芽生え、幕府も急速に近代化を進める必要に迫られました。
オランダから軍艦と教授団を招き、本格的な海軍伝習を開始しましたが、その当時、軍事科学には高度な数学が必要とされました。
その時に一番抜擢だったのが、西洋の数学でした。
というのも、和算は抽象的で、円の面積や多角形を求めるような、芸事的側面が強いのに対し、西洋数学は大砲の弾道学や物理学的な理論が豊富でした。
つまり、西洋の方が実戦向きだったと言えるのです。
さらに、和算家たちはこの国家的危機にあまり協力的ではなく、「日本の数学は西洋に劣らない」と過信し、現実を直視しようとしませんでした。
このような和算家の姿勢を見た幕府は、和算家を見限り、新世代の若者たちに西洋数学の習得を命じたのです。
和算家たちが意識を改め、実学に舵を切る前に、日本は明治維新を迎えてしまいました。
こうして和算という日本数学は、一斉に西洋数学へと塗り替えられたのです。
以降、教育制度は西洋式に改められ、現在でも学校で学ぶ数学も欧米式が主流となります。
和算は“旧時代の文化遺産”として博物館や研究対象となり、日本人の生活からは姿を消していきました。
まとめ
今回は、江戸時代の数学に潜んでいた“闇”についてご紹介しました。
まさか昔の数学が、あれほどまでに閉鎖的だったとは…驚かれた方も多いのではないでしょうか。
そう思うと、現代において誰もが自由に学べる、開かれた教育環境というのは、本当にありがたいことだと感じます。
僕自身、日々数学が好きで、記事を書いたり、証明を追いかけたりしていますが、今回の話はとても考えさせられるものでした。
というのも、数学者の仕事は、抽象的で高度な理論を探求することですが、
そのすべてが直接的に社会で役立つとは限りません。
むしろ、社会に応用されるまでには、いくつかの段階が必要だと思うのです。
たとえば、
- 純粋な理論を考える人
- その理論を社会に応用する仕組みを構想する人
- 応用された理論を現場で使いこなす人
このように、役割の異なる人たちがつながることで、数学はようやく実社会の役に立つものになるのだと思います。
そう考えると、江戸時代における数学の価値観のズレ、つまり、理論を追い求める和算家たちと、実用性を求めた町人たちとの間の断絶こそが、和算という文化が時代に取り残されていった大きな要因だったのかもしれませんね。
とは言え、間違いなく江戸の数学文化に宿っていた精神性は受け継いでいるはずなので、もし興味があれば和算について調べてみるのも面白いかもしれません。