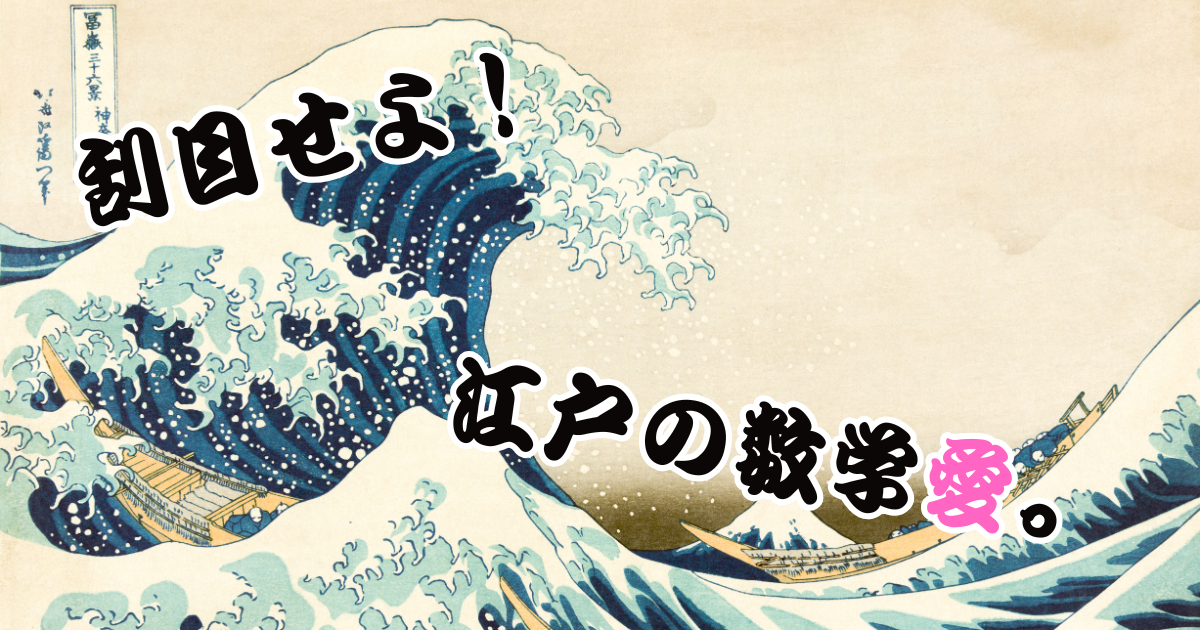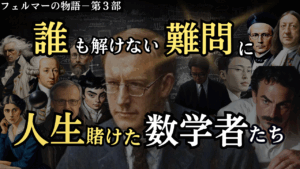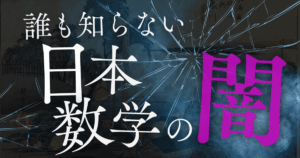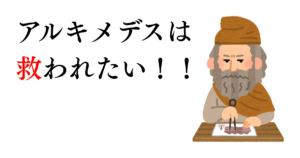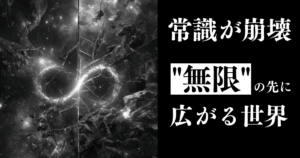神社に行けば、願い事などを絵馬に書いて奉納しますよね。
しかし、江戸時代は「数学の問題やその解法」を絵馬に書いて飾っていた――そんな文化があったことをご存知でしょうか?
しかも、それは一部の天才ではなく、町人も、農民も、時には子どもまでが奉納していたというのです!
「えぇ!?」と驚くでしょう笑
スマホも、インターネットも、YouTubeもない。
その時代の人々は数の世界に夢中になり、神に捧げるほどに数学に情熱を注いでいたのです。
とても不思議ですよね。
ということで、今回は知られざる江戸時代の数学文化をご紹介します。
江戸の数学「和算」とは
江戸時代の数学において、まず知っておいてほしい概念が「和算(わさん)」です。
和算とは、江戸時代の数学の呼び名です。

特に、「和算」は現代数学との対比で使われる用語です。
この和算、とても優れておりまして。
江戸時代の日本は鎖国中。
諸外国の数学的知識はほとんど入っていないにもかかわらず、日本の数学文化は、世界にも引けを取らないレベルだったそうです。



ルーツは大昔。奈良時代に輸入した中国の数学でしたが、それをベースに日本人が独自に発展させていきました。
特に当時の大数学者であった、関孝和(せきたかかず)は、独自に行列や高次方程式の解法に迫っていき、ヨーロッパに匹敵するほどの先進性を示しました。



ちなみに、円周率もかなり精度が高かったと言われています。
このように、江戸時代の数学は、日本人独自の論理と感性によって、かなり高いレベルにまで押し上げられていたのですね。
数学を神に奉納?算額という風習
そしてもう一つ、江戸時代の数学を代表するのが「算額(さんがく)」です。
この算額とは、文字通り、「算の額」。
すなわち、数学の問題を書きつけた額のことです。
僕たちが神社で願い事を絵馬に書いて、願掛けするように、江戸の人たちは、数学の問題、答え、そのプロセスを板に書いて、額にして神社や仏閣などに「絵馬」のように奉納したのでした。



数学を願掛けってなんだ?
と思うかもしれませんが、実はこの願掛けには、とても素敵な思想があります。
当時の人々は、お互いに数学の問題を出し合ったりして、解いていくことを1つの趣味として楽しんでいました。
数学の問題を一生懸命考えるわけですが、一筋縄ではいきません。
うーん、うーん…と考えに考え抜き、あれこれ試行錯誤して、そしてやっと「解けたーー!」となった時、人々は「これは神様のおかげだ!」と考えていたそうです。



こんなアイデアが閃いたのは、きっと神様が力を貸してくれたからに違いない!



神様が努力を認めてくださったのだわ!



これぞ、天が我に授けし理ぞ…!
そのような思いがあったからこそで、「できました!ありがとうございます!」という感謝の念と共に、数学を書いた絵馬を神社に願掛けしていたのです。



いやぁ〜!なんて素敵な話!!
この算額の習慣が始まった時期は、およそ寛文13年(1673年)あたりだと考えられています。
この年に刊行された「算法勿憚改(さんぽうふつたんかい)」という本に、算額が掲載されていたそうです。
ちなみに、この算額は現在も現存おりまして、、例えば八王子市の片倉にある住吉神社には、800枚ほど奉納されているそうです。



今度行ってみる予定です
また、算額は解けたことのお知らせだけでなく、「この問題、誰か解ける人いますか?」と次なる問題を飾る目的もありました。
すると、その算額を見つけた、腕に自信がある数学者がチャレンジするのでした。
まるで数学の問題をリレーのようにバトン形式で受け渡していく感じが、なんともユニークで粋な文化ですよね。



算額には、高度な幾何学問題や代数的な問いが書かれており、時には欧米の数学者が見ても驚くような内容が含まれていたとか。
学問の成果を神に感謝として捧げる。
その精神性には、日本人の学びに対する意識の高さを感じざるを得ませんよねぇ。
数学塾が全国に!地方ごとに違う、数学流派
江戸時代には、各地に「和算塾(わさんじゅく)」と呼ばれる数学の私塾が存在していました。
後世に名を残すような数学者は、最初ここに弟子入りをしていたそうです。



現代なら予備校の数学特化バージョンみたいな感じで、高度な数学技術が学べていたそうです。
そして、面白いことに各地ごとに和算に流派がありました。
各地ごとの流派や精神を受け継いだ一流数学者たちが、それぞれ和算塾を開講していたのですね。
これらの塾では、教師がオリジナルの問題集を用意し、生徒たちはその問題を解いていくというスタイルだったそうで。
口頭での教えに加えて、手書きで写されたテキストが回し読まれ、世代を超えて知識が継承されていきました。
また流派があるため、「この塾だけで使われている問題集」や「家伝の秘伝」とされる計算法なども存在しており、それらは代々の和算家に受け継がれました。
まさに“家業としての数学”ともいえる世界がそこにはあったというわけですね。



今は、全国統一的に同じ数学を学んでいますが、昔は違った!
ちなみに、算額が記録された書籍「算法勿憚改(さんぽうふつたんかい)」の著者「村瀬義益(むらせよします)」は、はじめ佐渡に伝わる「百川流」の数学を学び、その後は江戸に出て、磯村吉徳(いそむらよしのり)に弟子入りして、一流数学者に成り上がっていきました。
こんな感じで、数学者を志す者たちがいろんな流派を経由して一流になっていくのです。
数学のキャリアアップみたいな感じで、面白いですよね〜。



時には、別々の流派同士でライバル視し合ったり、いざこざもあったとか…苦笑
和算がみんなに愛された5つの理由
このような、江戸時代の数学文化をご紹介しました。
和算は日本中のみんなからとても愛されるものでした。
(もちろん、中には苦手な人もいたでしょうが…)
では、なぜそんなに人々は和算に熱中していたのでしょうか?
それには、いくつか考えられる説があるので、ご紹介します。
数学の名著「塵劫記」の大ヒット!
日本の和算文化の夜明けとも言えるのは、数学の歴史的名著とされる「塵劫記(じんこうき)」の大ヒットにあると考えられます。
この書物は、1627年(寛永4年)に吉田光由(よしだ みつよし)という京都の和算家によって書かれました。
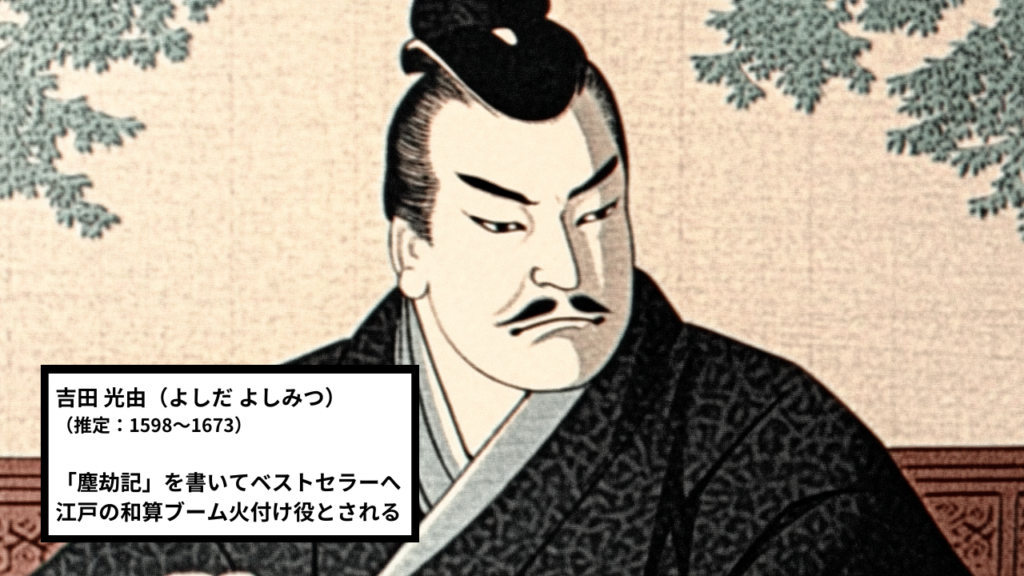
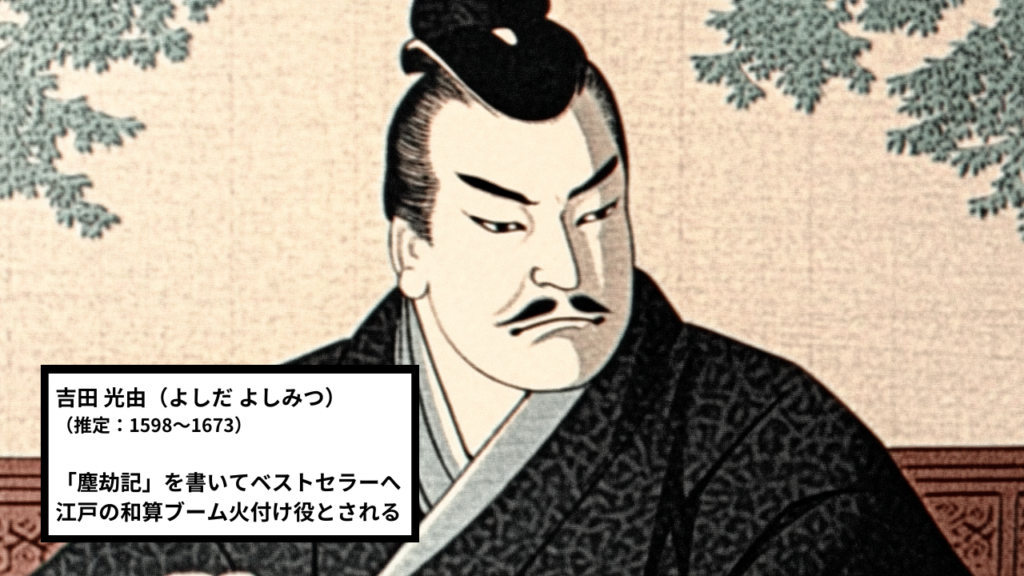
塵劫記の内容はシンプルです。
身近な計算や商人の取引、年貢の計算、さらには米の分配の仕方など、庶民の生活に直結した算術問題を、わかりやすく説明しています。
つまり、『塵劫記』は「実用数学のハウツー本」だったのです。
しかし、それだけではありません。
この本には、「算術の面白さ」や「知的なパズルとしての魅力」も含まれており、読者を飽きさせない工夫が随所に凝らされています。
例えば、謎かけのような問題や、数当て遊び、図を使った工夫問題などが掲載されており、「楽しい読み物」としても成立していたのです。
このユニークな算術書は、瞬く間に江戸中の人々の間に広まりました。
寺子屋や商家の必読書となり、写本や異版を含めて、200年以上にわたって版を重ね続けたとも言われています。
まさに“江戸時代の数学バイブル”と呼ぶにふさわしい存在だったのですね。



ただ、この本が有名になりすぎて、次々と海賊版が出まくりました。笑
そして、この大ヒット以降、次々の和算に関する書籍が登場しては、多くの人々に和算への興味関心を高めていったのです。
※江戸時代に出版された和算書
- 塵劫記(じんこうき/著者:吉田光吉/年代:1627年)
- 発微算法(はつびさんぽう/著者:関孝和/年代:1674年)
- 算法助術(さんぽうじょじゅつ/著者:建部賢弘/年代:1722年)
- 算法少女(さんぽうしょうじょ/著者:不明/年代:1760年)
- 括要算法(かつようさんぽう/著者:桑原盛行/年代:1783年)
などなど…。(年代はおおよそです。諸説あり)
身分関係なく、誰でも学べる!寺子屋と読み書きそろばん教育の普及


和算に限らず、教育の文化を大きく支えたのは、「寺子屋」の存在でしょう。
寺子屋は最盛期には日本全国で1万5千か所を超えたといわれ、町や村にひとつ、あるいはそれ以上あることも珍しくなかったそうです。
武士や商人の子どもたちだけでなく、農民や職人の子どもも通っていました。庶民や武士、町人などの身分関係なく、平等に教育の場として広く普及していました。
そういった意味では、教育の敷居をとても低くしてくれていたのですね。
ここで教えられていたのが、いわゆる「読み・書き・そろばん」。
和算塾のような数学特化ではありませんが、主に計算の基礎が学べていました。
特に「そろばん」は、商人にとって必須のスキルであり、帳簿づけや取引の計算の精度を高めるために重視されていました。
一方で、そろばんをきっかけに計算の面白さに目覚め、さらに発展的な数学――つまり和算の世界へ進んでいった人も多かったと言われています。
誰もが“計算の実用性”や“数そのものの面白さ”に触れられる社会基盤が、すでに整っていた――それこそが、和算が庶民にまで浸透した理由の1つと考えられるのではないでしょうか。
遊歴算家の存在


さらに!もっと面白いのは、遊歴算家(ゆうれきさんか)という人々の存在でした。
遊歴算家とは、いろんな場所へ訪ねては、その地域の数学愛好者へ数学を教える人々を指します。
この遊歴算家の人たちが、日本全国の和算レベルを高めていったと言っても過言ではありません。
当時の文化の中心は、江戸や京都、大阪周辺でした。
そのため、和算の最先端理論などもこれら都市に集中してしまいます。
逆を言えば、それ以外の地方には、あまり最先端な情報が届きづらいという欠点もありました。(当たり前ですが、スマホやネット、テレビなどはありません…。)
逆を言えば、それ以外の地方には、あまり最先端な情報が届きづらいという欠点もあります。
ここで活躍したのが、遊歴算家なのです。
彼らは収集した数学知識を、いろんな各地方へ伝えて回ったため、日本全国に様々な数学の知識が広まりました。
遊歴算家の活躍がもしなければ、もしかしたら和算は、都心部の愛好家だけのものになっていたかもしれません。
ですので、数学をいろんな場所へ行き、教え回った遊歴算家の人たちが、日本に和算文化を広めた大きな貢献をしていると言えるのです。
ちなみに、遊歴算家で有名な人物は山口和(やまぐち かず)です。
和算好きな権力者がいた
江戸時代の日本において、和算が広く花開いた理由のひとつに、「数学好きな権力者たちの存在」があります。
つまり、上に立つ人たちが本気で数学にハマっていた――という、ちょっと意外な事実です。
和算は、多くの人に愛されていた学問です。
ですので、和算が大好きな権力者がいても不思議ではありません。
江戸の大数学者、関孝和の流派を受け継いだ名だたる和算家、建部賢弘や山路主住らが活躍していたのですが、彼らはしばしば藩に仕えたり、幕府に登用されたりして、数学の研究に専念できる環境を得ていました。
つまり、数学ができると、権力者から愛され報酬もたっぷりいただける、みたいなある意味、オイシイ部分もあったのです笑



役人お抱えって、すごいですよ!
ちなみに、江戸時代に一流数学者と評された磯村吉徳は、和算の実力で二松藩に使えていたとされています。
このように、権力者自身も和算に関心があったことから、ある種、「和算ができる=偉い人に認められる」という風潮もあったのではと考えられます。
それがより、一層「和算を極めたい!」というモチベーションになった部分もあるのかもしれません。
「遊び」やアートとしての数学の魅力
数学の普遍性に魅了される人々の心は、時代を問わず存在します。
江戸時代の算額や和算も、この美しさを追求している一面があると言えると思えいます。
例えば、算額に掲載する和算の問題も、なるべく美しくして、プロセスや解法もシンプルにこだわることを意識していたそうです。
江戸時代は「禅」や「侘び寂び」の美意識も人々に浸透しており、“無駄のない構造”や“隠れた秩序”に美しさを見出す”という感覚が、和算の図形表現にも響いていたのかもしれません。
このように、和算は「勉強」や「職能訓練」としての数学ではなく、人生の楽しみ・美学の一部として愛されていたのです。
江戸の人々にとって、数式や図形は冷たく難解な記号ではなく、頭と心を刺激する“知的な遊戯”であり、“飾って見せたくなる美”でもあったと考えられるのです。
だからこそ、神社の一角に数式が掲げられ、人々が足を止めてその問題にうなる――
そんな風景が、あの時代の日常にあったのではないでしょうか。
おわりに
今回は、不思議な江戸数学の文化をご紹介しました。
学問を愛し、楽しみ、神に捧げ、そして生活の中で磨き上げていく。
数学って一見すると、無機質な数式の羅列のように感じる部分がありますが、そのイメージとは真逆の、人間味と熱量が満ちています。
時代が変わっても、その精神性は、今を生きる私たちにも何か活かせるものがあるのではないのかなと思います。
最後までお読みくださり、ありがとうございました!