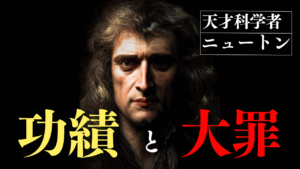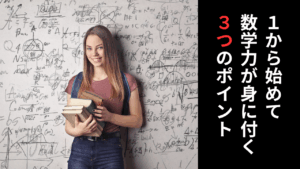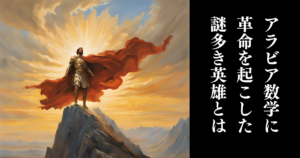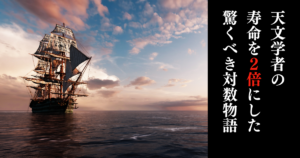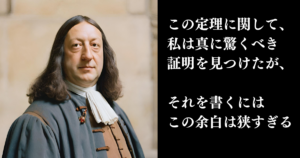どうも、マルタです。
数学者ってどんな印象?と聞かれると、だいたい
- イかれてる!
- 変人!
- 数式
- 屁理屈!
なんて印象があるんじゃないでしょうか。
実際、過去の数学者たちを調べていますが、大半が変なやつです笑
しかし、実は1700年代には、そんなイメージをぶっ壊す、とても気高く、社会的理念に命を燃やした異色の天才がいました。
しかも、数少ない女性数学者です。
彼女の名前は、マリア・ガエターナ・アグネシ。
あまり知られていませんが、後世に伝えるべき素晴らしい人物です。
その生き様たるや、徳が高く、高潔で、数学界のジャンヌダルク、もはやイエスといっても過言ではないでしょう!
彼女は女性が学問の場から排除されていた時代に、学問の平等性を訴え、社会のために生き抜いた女性でした。
ということで、今回はマリアの生涯と生い立ち、彼女が社会に向けて放ったメッセージなどをご紹介します。
ルネサンスの数学聖女マリアの生涯
9歳で語学をマスター
マリアは1718年、イタリアのミラノに生まれました。父親は裕福な学者で、家庭には書物が山ほどありました。これは、天才性が育まれるには絶好の環境でした。
また彼女の家には学者や知識人が集まるサロンが開かれており、大人との議論を交えながら、ますます彼女の才に磨きがかかっていきます。
マリア、わずか5歳でフランス語、7歳でギリシャ語、9歳でヘブライ語をマスターしたのでした。
わずか9歳にしてラテン語の公開講義をこなすという逸話が残っており、少女ながら驚異的な知性を見せつけていました。
しかも、その講義は、女性のための高等教育の必要性を主張したものでした。
当時の、ヨーロッパは女性差別がひどく、男性しか入学できない学校ばかりでした。
そんな社会の閉塞的な一面に、早くから一石を投じていたのですから驚きです。
さらに彼女は哲学や論理学、そして数学にも興味を持つようになります。
彼女は語学だけに限らず、哲学、論理学、そして数学に秀でており、まさに万能の才を備えていたのです。
10代で一流たちの数学をマスターする
マリアの驚くべき才能はいかんなく発揮されます。
まず自分の勉強をしながら、弟たち(彼女は21人兄弟の一番上)を教えていました。
その間に、なんとニュートン、ライプニッツ、フェルマー、デカルト、オイラー、ベルヌーイらの研究してきた数学をすべてマスターしたのでした。
その当時、彼女は「精神が物体から感覚的印象を受ける仕組みや、目や耳などの感覚が脳の器官に伝達する仕組み、そのほか、光の伝播や光の色などにも関心があったそうです。
恐るべし…。
アグネシ家では、定期的に知識人を開いたサロンが開かれていたのですが、マリアは天才すぎる故に、多くの知識人から質問されまくっていました。
10年かけて、世界初の女性による数学書が誕生!
マリアの名を不朽にしたのは、彼女が20代で書き上げた『Instituzioni Analitiche』(解析学教程)という大著です。
これ、現代で言えば「微分積分入門書」みたいなもので、しかも当時としては革命的にわかりやすく整理されていたんです。
ちなみに、この当時の彼女は、答えが出ない難しい問題に1日中取り組んだあと、夜目を覚まし、夢遊病のような状態で問題の正しい答えを書き上げたというエピソードがあります。
まごうことなき天才ですね。
アグネシの魔女
マリアは「アグネシの魔女」と呼ばれる曲線でも有名です。
なんで「魔女」?悪いことしたんか?って話ですが、そうではなく…。
実はこれ、翻訳ミスのせいです笑
イタリア語で「versiera(曲線)」をラテン語の「aversiera(魔女)」と混同してしまったんです。
なので、本来は「アグネシの曲線」なのが、「魔女の曲線」という、なんとも邪悪な名前になってしまったというオチなんですね笑
でもまぁ、名前のインパクトもあって、今もこの曲線は記憶に残っているわけですから、これは怪我の功名かもしれません。
晩年は貧者の看護に捧げた人生
マリアは数学の道を究めたあと、なんと一転して宗教と福祉の世界へと身を投じます。
父の死後、彼女はすべての資産を手放し、貧しい人々の看護に人生を捧げました。
44歳以降から1799年1月9日に81歳で永眠するまで続いたのでした。
貴族の娘として生まれながら、最期は病院で静かに息を引き取ったマリア。
彼女の生き方は、「学問は人のためにある」という信念を体現していたように思います。
数学者と聞くと、ド派手にいろいろやった数学者が目立ちがちである。
しかし、そのような歴史的な数学的貢献の背後には、静かに数学を発展させた人たちがいることを忘れてはならないのです。
マリアもまたそんな人物の1人なのではないでしょうか。